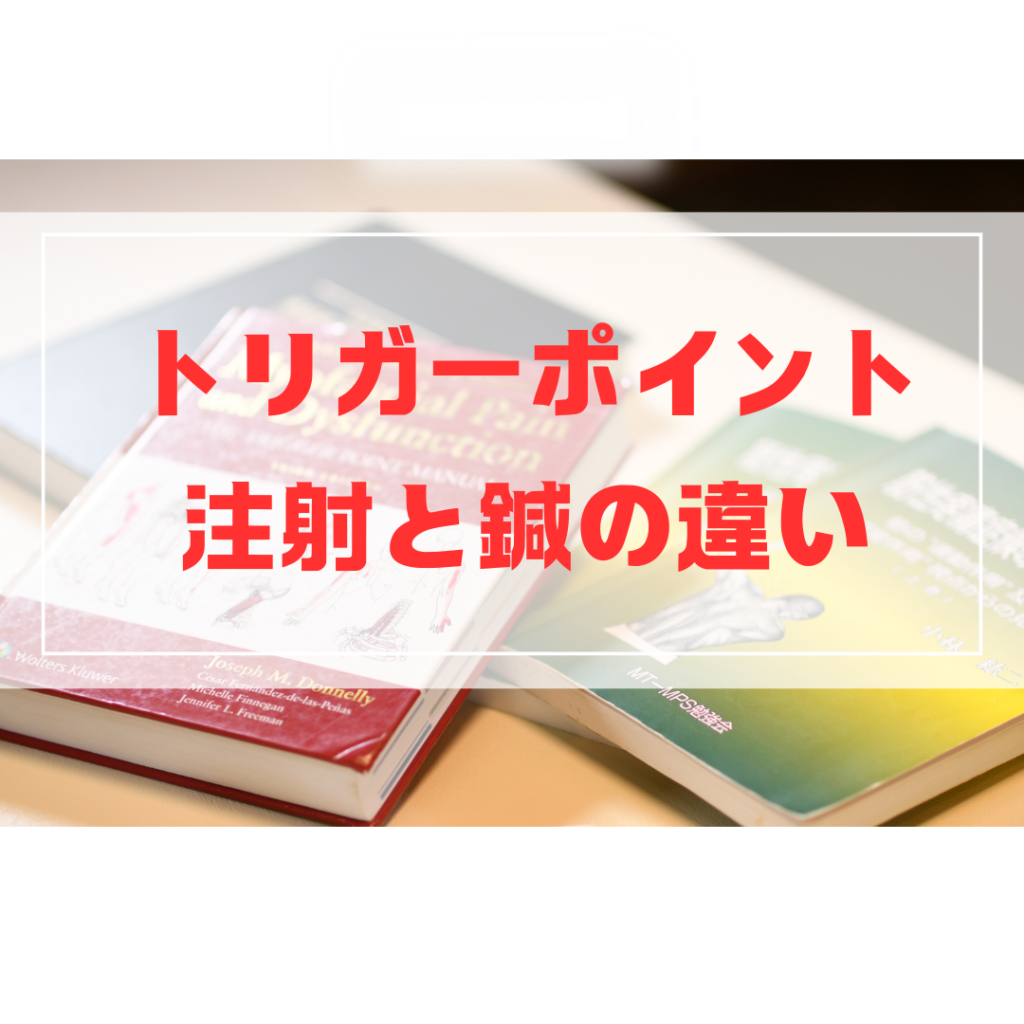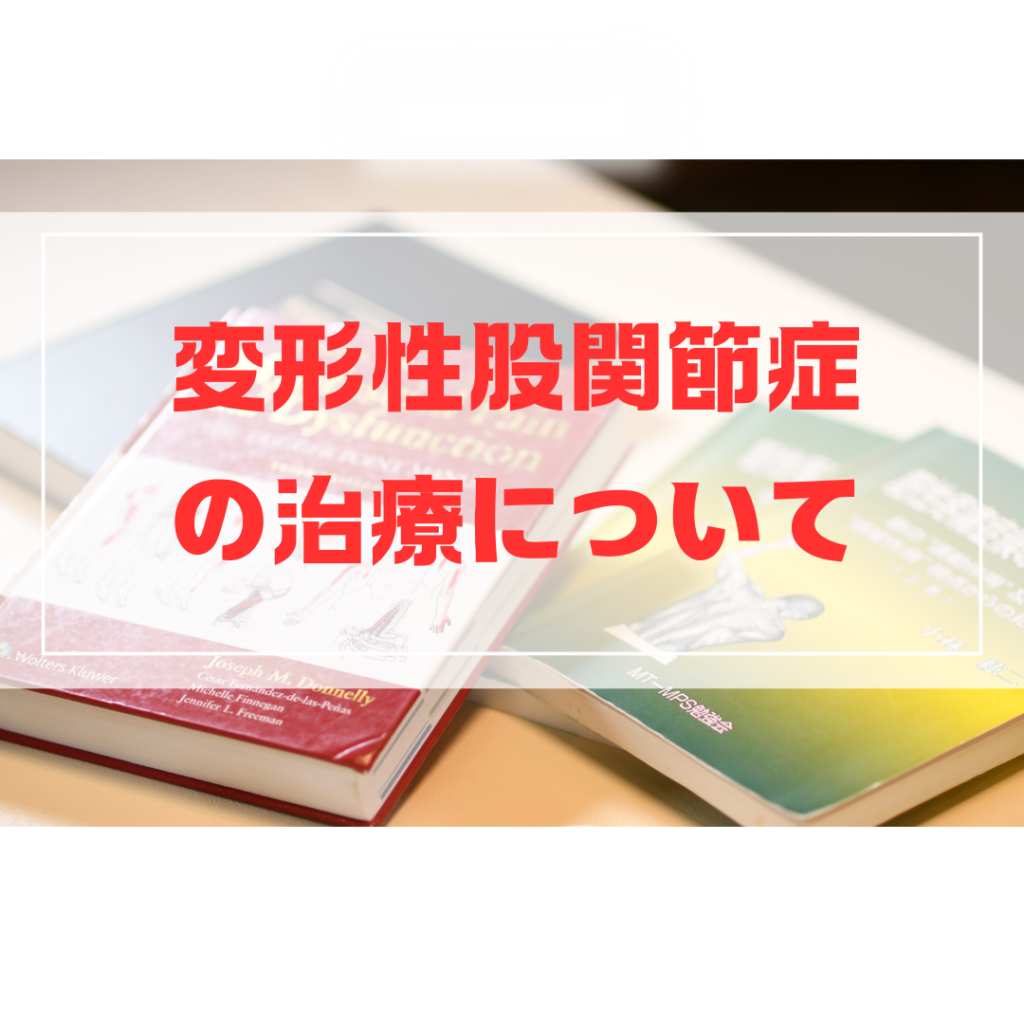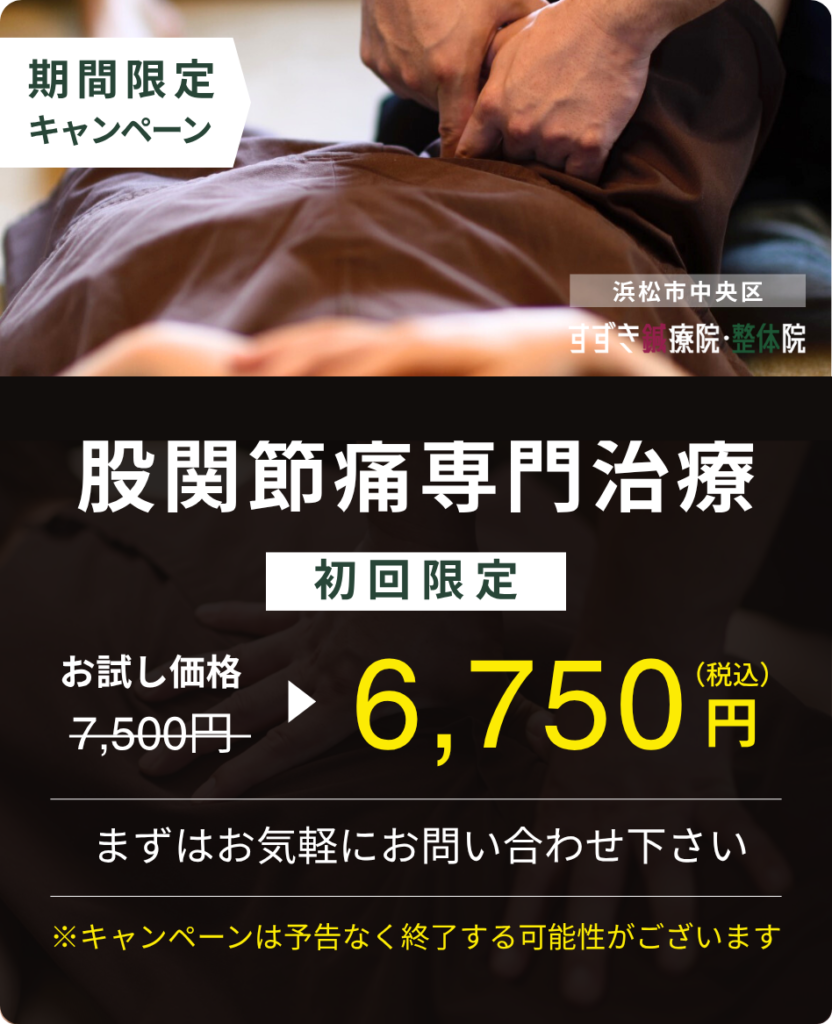筋・筋膜性疼痛症候群(MPS)とは?最新診断と治療
筋・筋膜性疼痛症候群(MPS)とは?2025年最新の診断・治療動向
肩こりや腰痛など、多くの慢性痛の背景に関わっているとされる筋・筋膜性疼痛症候群(Myofascial Pain Syndrome: MPS)。2025年現在、研究は進み、診断基準の標準化・発症メカニズムの解明・治療法の有効性に関する新しい知見が蓄積しています。
診断と有病率
診断の現状と課題
MPSの診断は、依然として触診によるトリガーポイント(TrP)の確認に大きく依存しています。一方で、研究間で用いられる基準の組み合わせは多様(報告では23種類)で、結果の比較や再現性に課題があります。
専門家コンセンサスで必須所見とされるのは以下の2点です。
- 索状硬結(Taut Band)内の圧痛点の存在
- 圧痛点刺激で生じる関連痛(放散痛)
有病率(どのくらいの人がなる?)
- 一般人口では、MPSの有病率は最大20%と報告
- 慢性痛専門クリニック受診者では85〜93%と非常に高率
発症メカニズム(なぜMPSが起こるのか)
エネルギー危機仮説
筋の酷使や反復動作で局所の血流が低下し、酸素・栄養不足からATPが枯渇。その結果、カルシウムポンプが働かず筋線維が弛緩できず、索状硬結と過敏な圧痛が生じると考えられています。
神経の感作(痛みの慢性化)
トリガーポイントからの侵害入力が続くと、脊髄・脳の神経系が過敏化(中枢感作)。痛みが増幅・遷延し、慢性化の悪循環につながります。
治療法の最新エビデンス
侵襲的治療(注射・鍼)
- トリガーポイント注射(TPI):局所麻酔薬を用いた注射はMPSに対して有効性を支持する十分な証拠あり。
- ドライニードリング(鍼治療):プラセボと比較して痛み軽減・機能改善に有効。
- 比較の要点:短期の疼痛軽減はTPIがやや優位の可能性。一方、長期効果は同等で、薬剤を使わない鍼治療は安全性に優位。
非侵襲的治療(薬を使わない方法)
- 体外衝撃波治療(ESWT):有効性を示す報告あり。ただし他治療より常に優れるとまでは言い難い。
- 手技療法(筋膜リリース・圧迫):痛み軽減に有効と示唆。
- 運動療法・ストレッチ:改善と再発予防に非常に重要。
- 薬物療法:NSAIDs等は補助的位置づけ。単独使用は推奨度が低い。
まとめ
MPSは「単なるコリ」ではなく、慢性痛の主要因として注目される疾患です。2025年現在、TPI・鍼治療・手技療法・運動療法にエビデンスが集積。とくに安全性や長期の機能改善を考えると、薬剤を使わないアプローチの価値が高まっています。
浜松市で慢性痛やトリガーポイントにお悩みの方は、すずき鍼療院・整体院へお気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q. MPSはレントゲンやMRIでわかりますか?
A. 画像検査では骨や関節の異常はわかりますが、筋・筋膜やトリガーポイントは映りません。触診や機能評価が診断に重要です。
Q. 注射と鍼治療はどちらが良いですか?
A. 短期の痛み抑制は注射がやや優位。一方で長期効果は同等で、薬剤リスクを避けたい方には鍼治療が適しています。症状やご希望に合わせて選択します。
Q. 自分でできる対策はありますか?
A. ストレッチ・軽い有酸素運動・姿勢の見直しが役立ちます。再発予防には生活習慣の調整と、必要に応じた専門治療の併用がおすすめです。
この記事の執筆者
鈴木 雄亮(すずき鍼療院・整体院 院長/鍼灸師)
筋筋膜性疼痛症候群(MPS)やトリガーポイント治療を専門とし、腰痛・坐骨神経痛・脊柱管狭窄症など慢性症状の改善を得意としています。
大阪手技療法研究会やREXトリガーポイント研究会で研鑽を積み、最新の知見を臨床に取り入れながら施術を行っています。